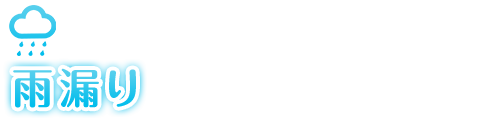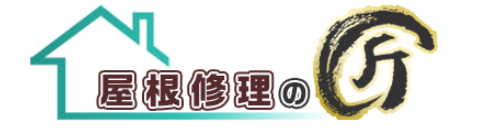かつては「給料が高い」「手に職がつく」といった理由で人気を集めていた建設・製造・サービス業などの現場職ですが、近年、若手世代、特に20代の価値観は大きく変化しています。
求人を出しても応募が少ない、面接に来ても長続きしない――。そんな悩みを抱える企業が増える中で、「今の20代が何を重視して仕事を選んでいるのか」を理解することが、採用成功の大きな鍵となります。
■ 20代が仕事に求めるのは「安心」と「生活の質」

一昔前のように「多少きつくても稼げればいい」「修行だから我慢する」という価値観は、今の20代には通用しません。
もちろん給料が低くて良いというわけではありませんが、それ以上に彼らが求めているのは“生活の安定”と“心の余裕”です。
具体的には、休日・労働時間・福利厚生・職場の雰囲気といった「働く環境そのもの」を重視する傾向が非常に強いです。
たとえば、「完全週休二日制」「年間休日120日以上」「残業少なめ」「有給取得率〇%」といった言葉があるだけで、応募率が2倍、3倍と変わるケースも珍しくありません。
それほど、今の若手にとって“休める環境”は重要な要素になっています。
■ 年間休日は「110日」がひとつの目安
求人票で応募者が真っ先に目を通すのが年間休日の欄です。
現在の日本の平均はおおよそ115日前後ですが、建設業や製造業では100日を下回る企業も少なくありません。
この「年間休日の少なさ」が若手の応募を妨げている現実があります。
20代の求職者は、仕事とプライベートをしっかり分けたいと考えています。
たとえば、「年間休日120日・完全週休二日制」の企業と、「年間休日90日・隔週休二日制」の企業では、仕事内容が同じでも前者に応募が集中します。
つまり、**休日数は給料と同じくらい重要な“待遇条件”**として認識されているのです。
また、休日の「取りやすさ」も大切です。カレンダー通りに休める、家庭や趣味の予定に合わせて有給を使える――そんな柔軟な運用があるだけでも、企業の印象は大きく変わります。
「休めない会社」ではなく「休みを取れる会社」であることをアピールすることが、20代採用の第一歩です。
■ 福利厚生の充実は“安心”を生む

次に注目されるのが福利厚生です。
特に20代は将来に対して不安を抱く世代でもあります。
そのため、社会保険完備や交通費支給などの基本的な制度はもちろん、住宅手当・資格取得支援・家族手当・退職金制度といった項目を重視しています。
これらの制度は、単なるお金の支援だけでなく、「この会社は従業員を大切にしている」という信頼感を生み出します。
また最近では、次のような福利厚生も注目を集めています。
-
健康に関する支援:定期健診、メンタルケア、インフルエンザ予防接種補助など
-
働き方支援:リモートワーク制度、勤務時間の選択制、週休3日制など
-
ライフイベント支援:出産・育児休暇、介護休暇、子ども手当など
特に20代後半の層は「結婚」「出産」「マイホーム購入」など将来設計を考える時期でもあります。
そのため、福利厚生の充実は給与以上に“長く働けるかどうか”を判断する材料になっています。
■ 20代が求める“職場の空気感”
どれだけ待遇が良くても、職場の人間関係がギスギスしていたり、上司との距離が遠かったりすると、若手は長続きしません。
今の20代は、「叱られて育つ」よりも「相談しながら成長したい」と考える傾向があります。
つまり、風通しの良い職場やチームワークを大切にする環境を強く求めているのです。
実際、「社長や上司が話しやすい」「先輩が面倒見がいい」「質問しやすい雰囲気」といった口コミがある企業は、採用率も定着率も高い傾向にあります。
求人票の中でも、単に「アットホームな職場です」と書くだけでなく、
「20代社員も多く在籍」「入社後は先輩が1対1でサポート」「社長とも意見交換できる環境」など、具体的なエピソードで安心感を伝えることが大切です。
■ 「働きやすさ」を数字で見せる求人が支持される

20代は情報に敏感で、数字による客観的な比較を好みます。
そのため、求人内容も「感覚的な表現」より「具体的な数値」を示す方が信頼されやすいです。
例として、
-
年間休日:120日(完全週休二日制)
-
有給取得率:75%
-
平均残業時間:月10時間以下
-
離職率:過去3年で10%以下
こうした数字が並ぶだけで「しっかりした会社」という印象を与えることができます。
逆に、「休みは多め」「残業ほぼなし」といった曖昧な表現は、若手に不信感を与えやすいです。
20代の応募者は「リアルな情報」を求めています。だからこそ、事実に基づいた透明性のある募集要項を出すことが大切です。
■ 若手の「成長意欲」に応える仕組みを
今の20代は、“楽をしたい”のではなく、“納得して働きたい”世代です。
仕事の意義や自分の成長を感じられるかどうかを大切にしています。
そのため、求人には「学べる環境」や「キャリアアップ制度」を明示することが効果的です。
たとえば、
-
資格取得費用の全額支給
-
社内研修制度や勉強会の実施
-
未経験者向けの育成マニュアル
-
職長・管理職へのステップアップ例
こうした情報があるだけで、20代の応募者は「この会社で成長できそう」と感じます。
“育てる姿勢を見せる”ことが、今の採用市場では何よりの武器になります。
■ SNS時代の「企業の見え方」が採用を左右する

今の若者は、求人サイトだけでなく、InstagramやTikTok、Googleマップの口コミなどを通じて会社の雰囲気をリサーチしています。
求人票に書いてあることと、SNSで見える実際の雰囲気が一致していれば「信頼できる会社」として認識されますが、逆にギャップがあると一気に信頼を失います。
つまり、今の採用活動は「求人票=会社のすべて」ではなく、日々の発信や社員の声も含めて“ブランディング”が問われる時代になっているのです。
休みの多さや福利厚生を整えることはもちろんですが、それを“どう伝えるか”も同じくらい重要になっています。
■ 求人票は「会社の価値観」を伝える場
募集要項は、単なる条件の羅列ではなく、会社の姿勢を伝えるメッセージでもあります。
「社員を大切にしている」「無理なく働ける」「成長を応援している」といった想いが文章から感じ取れる求人は、それだけで応募者の心に響きます。
20代は数字を見ながらも、“言葉の温度”にも敏感です。
どんな小さな一文でも、真摯さや誠実さを感じられるかが鍵になります。
■ まとめ ― 若者の目線で「働き方」を見直す
求人募集の目的は、ただ人を集めることではなく、「長く活躍してもらう仲間を見つけること」です。
そのためには、今の20代が何を大切にしているのかを理解し、その価値観に寄り添うことが欠かせません。
彼らが求めているのは、
-
休みが取れる
-
福利厚生が整っている
-
人間関係が良い
-
成長できる
という、ごく当たり前の“働きやすさ”です。
これらを正直に整え、伝えることこそ、これからの採用成功の近道です。
そして、その変化を恐れず実践する企業こそが、次の世代の信頼を勝ち取り、未来へと続く組織をつくっていくのです。