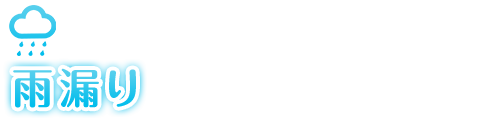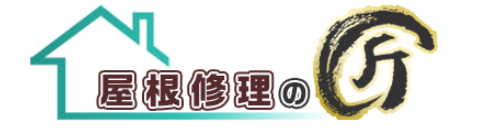日本の建設現場にとって、梅雨は一年の中でも特に悩ましい季節だ。
特に屋外作業を中心とする職人たちにとって、雨は仕事の進行を大きく左右する。天気予報を見ながら予定を組むものの、梅雨前線が停滞すれば数日、時には一週間以上現場が止まることもある。そんなとき、多くの職人が頭を悩ませるのが「給与」だ。
■ 職人の給与体系は“日当制”が主流

建設業界における職人の給与は、一般的な月給制とは異なり、日当制が多い。
つまり「働いた日数 × 日当金額」が収入になる仕組みだ。
日当の金額は職種・経験・地域によって幅があるが、たとえば関西圏の左官・塗装・鉄筋・解体・外構などの職人であれば、1日あたり12,000円~18,000円前後が相場となる。熟練の親方クラスになると20,000円を超えるケースも珍しくない。
このシンプルな体系は、技術や頑張りがそのまま報酬に反映されやすいという利点がある一方で、天候や現場状況によって収入が不安定になりやすいというリスクも抱えている。特に梅雨のように長期間にわたって雨が続く時期は、日当制の職人たちにとって「働けない=収入が減る」という現実が重くのしかかるのだ。
■ 梅雨が職人の生活を直撃する理由
梅雨の時期に最も影響を受けるのは、屋根工事・外壁塗装・防水・基礎工事など、屋外作業が中心の職種だ。
これらの作業は、雨が降ると安全面や品質面の理由から中止となることが多い。たとえば屋根の上での作業は滑落の危険があり、塗装工事では塗料が乾かずムラや剥離の原因になる。防水工事でも乾燥工程が重要なため、雨天は避けざるを得ない。
結果として、梅雨の一か月間で「稼働できる日数」が大きく減る。
たとえば通常なら月に25日程度稼働して30万円前後の収入を得ていた職人でも、梅雨時期には15日程度しか働けず20万円を下回るということも珍しくない。逆に、雨の日に屋内作業が可能な職種(内装・電気・設備など)は比較的安定する傾向にある。
■ 雨天保証・待機手当という考え方

こうした季節的なリスクを軽減するために、一部の会社では「雨天保証」や「待機手当」といった制度を設けている。
たとえば、雨で作業が中止になった場合でも半日分の日当を支給する、または一定回数までは全額保証といった形だ。
これは職人にとって大きな安心材料となるが、すべての会社が導入できるわけではない。特に中小の施工業者では、受注金額に余裕がなく、天候による休工を完全にカバーするのは難しいのが現実だ。
一方で、最近では職人の定着率を高めるために、あえてこうした保証制度を取り入れる企業も増えている。雨天保証を導入することで、職人の生活を守り、安心して長く働ける環境を整えようという動きだ。
職人の側から見ても、仕事の安定性を重視してそうした会社を選ぶ傾向が強まっている。
■ 梅雨時期にできる“収入確保”の工夫

梅雨の間、ただじっと晴れを待つだけではもったいない。多くの職人たちは、この時期を「次に備える時間」として活用している。
たとえば以下のような工夫だ。
-
倉庫整理や道具のメンテナンス
雨の日こそ、現場ではできない作業を進める絶好のタイミングだ。
工具の点検や塗料の在庫整理など、日頃後回しにしがちな業務を行うことで、梅雨明け後の現場がスムーズに動く。 -
資格取得や技能講習の受講
玉掛けや高所作業車、職長・安全衛生責任者など、建設業界では多くの資格が存在する。雨で現場が止まる時期に勉強や講習を進めておくことで、梅雨明け後の仕事幅を広げることができる。 -
室内リフォームや応援仕事の受託
内装や設備系の仲間に声をかけて一時的に屋内現場を手伝うなど、柔軟に働くことで収入の落ち込みを抑えるケースもある。
このように、梅雨は単なる“休み”ではなく“準備期間”と捉えることで、職人としての成長や安定に繋がるのだ。
■ 会社側ができるサポートとは
企業や親方の立場から見ても、梅雨時期の対策は非常に重要だ。
職人の収入が減れば生活が不安定になり、結果として離職や人手不足につながる可能性もある。
そのため、次のようなサポートを検討する企業も増えている。
-
年間を通した報酬の平準化
忙しい夏場や秋口に少し高めの日当を設定し、雨が多い時期の減収をカバーする仕組み。 -
工期調整による分散化
梅雨前に外作業を集中させ、雨が続く時期には屋内仕上げ工程を多くするなど、スケジュール全体でリスクを分散する。 -
固定給+歩合制の導入
完全日当制ではなく、最低保証を設けて安定感を持たせる形。特に若手や家庭持ちの職人にとって安心感が大きい。
こうした工夫が「雨でも不安にならない現場づくり」につながり、結果的にチーム全体のモチベーションを保つことにも寄与している。
■ 梅雨における“心の負担”と向き合う

梅雨の長雨は、収入面だけでなく、精神的なストレスも大きい。
毎朝天気予報を確認しながら「今日も中止か」と肩を落とす職人も多い。身体を動かす仕事だからこそ、急に休みが増えるとリズムが狂い、焦りや不安が募るのだ。
また、家庭を持つ職人の場合は、子どもの教育費や住宅ローンなど、固定支出が多い。梅雨時期の収入減は家計にも直接響くため、「休んでも気が休まらない」という声もよく聞く。
そのため、最近では職人仲間同士で情報共有を行ったり、SNSを通じて空いている現場を紹介し合う動きも増えている。仕事を“個”ではなく“ネットワーク”で支え合う形が、次第に広がりつつあるのだ。
■ 雨に強い働き方を考える
時代の変化とともに、職人の働き方も少しずつ変わり始めている。
かつては完全に現場中心だった働き方も、最近ではオンライン見積もりや現場管理アプリの導入など、デジタルの活用が進んでいる。雨で現場が止まっても、見積書や写真整理、顧客対応など「デスクワーク的な業務」を進めることで、次の仕事につなげられるのだ。
さらに、施工業者の中には「屋内・屋外を組み合わせた職種展開」を進めるところもある。
たとえば塗装工事に加えて内装クロス貼りも扱う、外構職人が左官技術を学んで店舗改修にも対応する――といった多能工化が進めば、梅雨時でも安定した収入を確保しやすくなる。
これは職人自身のスキルアップにもつながり、長期的には「天候に左右されない職人」への道でもある。
■ 梅雨を乗り越えた先にある“信頼と安定”
梅雨明けの空の下で再び現場が動き出すと、職人たちは改めて「やっぱりこの仕事が好きだ」と感じるという。
手が止まる時期をどう過ごすかは、人によって差が出る。しかし、梅雨の期間を前向きに活用した職人ほど、次の繁忙期でしっかり稼ぎ、信頼を積み上げていく。
建設業は自然とともに生きる仕事だ。
天候に左右される厳しさもあるが、それを理解し、準備し、柔軟に対応できる人こそが長く続けられる職人となる。
そして、そうした職人を大切にする企業が増えることで、業界全体の安定にもつながっていくだろう。
■ まとめ ― 雨の日も「仕事の日」に変える発想を
梅雨は、職人にとって試練の季節でありながら、実は大きなチャンスの時期でもある。
天気に振り回されるのではなく、雨の日こそ「技術を磨く」「仲間と支え合う」「次の仕事を仕込む」時間に変えていく。
その意識の差が、梅雨明けの成果に直結する。
日当制という仕組みは確かにシビアだが、その分、努力と工夫がそのまま結果に返ってくる世界でもある。
梅雨時期の苦労を知り、対策を積み重ねてきた職人ほど、周囲からの信頼も厚くなる。
そしてその信頼こそが、次の現場・次の仕事を呼び込み、安定した収入と豊かな職人人生をつくっていくのだ。