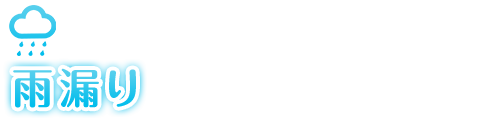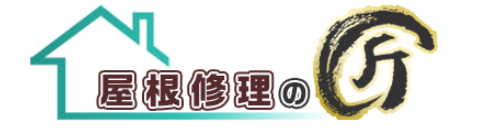防水工の職業は、建物の仕上げ工程の一部として重要な役割をになっています。主に屋根、屋上、外壁、ベランダ、窓サッシの周囲、水回りなどに防水処理を施すことで、建物内部への水の浸入を防ぎます。
この防水処理の主な目的は、建物の構造を維持し、雨漏りやカビやシミ、色褪せを防ぐことにあります。防水作業は、新築建築の仕上げ段階だけでなく、定期的なメンテナンスとしても実施されることが一般的です。
防水工の仕事内容とは

防水工事には様々な手法が存在し、その場所に最適な方法を防水工が施行します。素地により工事の流れが異なるため、ここでは屋根などで行われる代表的な防水作業について説明します。
1. 外壁のサッシと壁の隙間に防水材を注入する。
2. 外壁の防水処理を実施する。
3. 屋根にアスファルトや合成樹脂を塗布、または貼り付ける。
4. 屋根に防水フィルムやシートを敷き、固定する。
5. アスファルト等の高温材料を取り扱う。
6. 屋根材を取り付ける前に、屋根の掃除や不要物の除去を行う。
また、工事後は定期的なメンテナンスも重要です。新築だけでなく、老朽化や災害により損傷した建物の防水工事も手掛けます。その際には、損傷状況を細かく調べ、適した工事手法を選定します。
防水工としての働き方

防水工事を専門にする会社で働くことが一般的です。経験を積んだ後に独立し、自身の会社を立ち上げるケースもあります。
勤務時間は会社によって異なりますが、多くは朝8時から夕方17時頃までの勤務が一般的です。ただし、現場が遠い場合は早朝に集合して移動することもあります。
休日は日曜日が一般的ですが、工事のスケジュールや締め切りに応じて日曜出勤が必要な場合もあります。また、屋外作業が多いため、天気によっては作業ができない日もあります。
給料に関しては、多くの会社が月給制を採用していますが、雨天や台風などの影響で工事ができないと収入に影響が出るリスクもあります。
そのため、日給制を選べる会社や、最低賃金を保証する会社、工事ができない日はメンテナンスや事務作業を行う会社も存在します。
防水工になるには?

防水工事を請け負う会社に就職し見習いから始める
防水工を目指す場合、多くの人が学校を卒業後、防水工事を手掛ける会社に就職します。一般的に、これらの企業は学歴や特定の資格を必須としていないことが多く、未経験からスタートすることも珍しくありません。仕事は実務を通じて学ぶことが業界では一般的です。
しかし、専門学校や職業訓練学校であらかじめ防水工事や建築関連の技術を学んでいると、就職時により良い条件を得られる可能性が高くなります。
また、中途採用の場合、普通自動車免許の保持が条件とされることもありますし、新卒の場合でも入社後に免許取得を求められることがあります。
技術の習得には、工法によって必要な期間が異なりますが、一般的には仕事に慣れ、一通りこなせるようになるまでに数年を要すると言われています。
防水工職人に求められるもの

防水工の仕事には特定のスキルや資質が求められます。
集中力と丁寧な作業
防水工事では細部にわたる注意が必要です。手抜き作業は見栄えが悪くなるだけでなく、将来的な建物の問題につながり、クレームの原因にもなりえます。
施工の際は集中して丁寧に作業する能力は必須です。また、集中が途切れると怪我のリスクも高まります。
体力と体調管理
工事は暑さや寒さなどの厳しい環境下でも行われます。頻繁に体調を崩してしまうと工事の遅延につながり、問題を引き起こすことも。体力が必要なのはもちろん、自己の健康管理も重要です。
手先の器用さ
かなづちやのこぎりなどの工具やドリルなどの電動工具を使用します。作業には手先の器用さが求められます。
コミュニケーション能力
同じ現場で働く仲間との良好なコミュニケーションが欠かせません。仕事の打ち合わせから休憩時の会話に至るまで、他者との関係構築がスムーズな仕事に繋がります。
手作業が好きなこと
建物の防水加工は、さまざまな道具を駆使する手作業が中心です。このような作業が好きな人には、防水工の仕事は特に魅力的です。
また、防水工には取得すると転職に有利になったり、会社によっては給与アップが期待できるものがあります。
資格取得について

防水施工技能士
この国家資格は、防水施工に関する技能のレベルが評価されるもので、厚生労働省が認定しています。合格すると、技能士としての認定と合格証書が交付されます。
1級と2級の2つのレベルがあり、どちらも実技試験と学科試験が含まれます。試験内容には、施工方法、塗料の取り扱い、関連する法律、建築に関する知識などが含まれています。
受験資格は、1級が実務経験7年以上、2級が実務経験2年以上となっています。多くの場合、防水工として働きながら資格を取得します。資格を取得すると、所属する会社によっては資格手当が付与されることもあり、昇進や昇給のチャンスも広がります。試験は中央職業能力開発協会が実施し、受験は各都道府県の職業能力開発協会を通じて申し込むことができます。
危険物取扱者
防水工の仕事において、ウレタン防水材料のような危険物を扱うことがあるため、危険物取扱者の資格を持っていると仕事の範囲が広がります。危険物取扱者には甲種、乙種、丙種の3種類があり、甲種資格を取得すれば、すべての危険物の取り扱いや立ち合いが可能になります。ただし、甲種の試験は難易度が高いです。
この資格の試験は一般財団法人消防試験研究センターによって実施されており、詳細情報は同センターのホームページで確認することができます。資格を取得することにより、防水工としてより多くの業務に対応できるようになり、専門性を高めることが可能です。
有機溶剤作業主任者
労働安全衛生法に基づく国家資格である有機溶剤作業主任者は、都道府県の労働基準協会などが定期的に開催する講習会を受講し、修了試験に合格することで取得できます。
この資格は、有機溶剤を使用する作業の際に必要とされるもので、有機溶剤を扱う際の責任者としての役割を担います。
防水作業においても有機溶剤が使用されることがあるため、この資格を持っていると作業の幅が広がり、より多くの現場で活躍することが可能になります。
キャリアアップについて

防水工としてのキャリアアップには、現場での経験を積んでステップアップする方法があります。防水工事には、防水層の種類や工法、使用する材料、建物の状態に応じた多様な作業が含まれます。
入職後すぐに全てをこなせるわけではなく、通常は数年かけて技術を習得します。
多くの会社や組合では、職員のスキル向上のために研修の機会を提供し、技能の向上をサポートしています。一人前の職人としての技能を身につければ、現場指揮や監督の役割を担う職長への昇進が可能です。
さらに、防水施工技能士や有機溶剤作業主任者などの資格を取得することで、独立して自分の事業を立ち上げる道もあります。最初は個人で仕事を請け負い、事業が拡大すると従業員を雇うことも一般的です。こうしたキャリアパスを通じて、防水工としての経験と技能をさらに発展させることができます。
今回は防水工職人についてご紹介しました。
手に職をつけることで独立を目指して収入アップも目指せる職業です。
建築業界に興味がある方は一度検討してみてください。