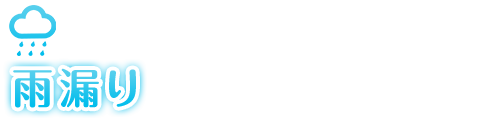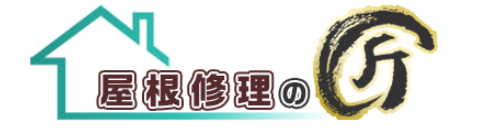建築現場を見て、思わず見入ってしまうことはありませんか。何もない更地に、戸建て住宅やマンション、さらに天にも届くような超高層ビルが建てられていく様は、とても興味深いものです。建築現場では、様々な専門技術を身に付けた職人が集い、それぞれの能力を発揮し、協力しながら建物を作り上げています。
「大工さん」も建築施工を担う職種のひとつです。その歴史は古く、飛鳥時代にさかのぼるといわれており、当時から、高度な建築技術を用いて、多くの建造物を建てていました。たとえば、今も残る世界最古の木造建築として、世界遺産に認定された「法隆寺」をはじめ、堅固な城郭や荘厳な寺社仏閣をも生み出してきた彼らの仕事は、世界的にも高い評価を受けています。
そこで今回は、歴史と経験によって培われてきた技術を受け継ぎ、多種多様な建築現場で活躍する大工さんの仕事を調べてみました。

大工さんの基本仕事「住宅」が建つまでの流れ
「大工」とは、設計図を基に建物の建築や増改築、修理(リフォーム、リノベーションほか)、内装工事などを行う仕事です。主な作業内容は、建築物の骨組みである柱や梁、壁、屋根、床、階段といった木造部分の加工や組み立て、さらには建築物内部の木製設備や家具の製作・取り付けなどがあげられます。木造住宅の建設が中心ですが、近年増加している、鉄骨造・鉄筋コンクリート造建築において、木質系の建材を使った内部設備を担うことも少なくありません。
大工さんは、建築工程に応じて様ざまな職種に分かれ、それぞれ専門的な技術を有しています。そのため、構造施工には絶対に欠かせない存在です。大工さんの詳しい職種を紹介する前に、まず、一般住宅ができるまでの流れをつかんでおきましょう。
住宅ができるまで

・設計・建築許可の取得:取得した土地に対して、施主と建築家や設計事務所、施工主との間で打ち合わせを行い、予算、敷地の形状や周辺環境などを考慮しながらデザインや仕様を決め、設計図を作成。その後、建築許可を得るために、必要書類(設計図面や建築計画書、予算計画書など)を市役所や建設業界の検査機関などで申請を行います。
・土地の整備:住宅や建築物を建設する前に行われる重要な作業のひとつで、具体的には、測量をはじめ、地盤調査や地形の整備、敷地のレベリング、道路の整備、下水道や上水道の設備などが含まれます。地盤が軟弱な場合には、地盤改良が必要になる場合もあります。
・基礎工事・建築工事:上記のような着工準備が終わると、建築施工を請け負った建築会社による工事が開始されます。大工さんが主に活躍するのはこれらの工事で、下記のような作業を行います。
○基礎工事:建物と地盤をつなぎ、建物の重さを支えるための土台を作る工事です。基礎には主に鉄筋とコンクリートが使われており、地震などの振動、湿気などから建物を守る役割も担っています。一般住宅で多く用いられているのは、主となる柱や壁の下に連続して基礎を置く「布基礎」と、床下全面に鉄筋コンクリート入り基礎を配する「ベタ基礎」です。
○型枠工事:基礎工事のひとつで、基礎の立ち上がり部分(水平面から垂直方向に立ち上がった部材)に型枠を作り、コンクリートを流し込み、建物の構造体を作成することです。この時、基礎コンクリートと木の柱をつなぐ「アンカーボルト」も設置します。

○躯体工事:基礎工事を含む、建物の主要構造部を作る工事のことです。土台、柱、桁、梁などの部材を元に、在来工法である「木造軸組工法」や「2×4(ツーバイフォー)工法」といった技術を用いて、建築構造を支える骨組みを組み立てていきます。

・屋根工事:屋根の構造材が組み上げられたら、構造用合板を貼り、その上に透湿防水シートを施工。断熱遮音工事などを行ない、瓦や鉄板、金属、スレートといった屋根材を葺く工事になります。現場にある建築資材を雨に濡らさないため、早めに行うこともあるようです。
・サッシ設置工事:柱と柱の間にサッシや玄関ドアを取り付けます。
・中間検査:屋根工事をひとつの区切りとして、工事途中に建物の構造の安全性をチェックする中間検査を行います。これは、阪神・淡路大震災で倒壊した建物が多かったことから、建築物の安全性向上のために導入された新制度です。中間検査を義務付けられる建物は、知事や市長といった、それぞれの特定行政庁が自由に決定できるので、詳細は自治体に問い合わせる必要があります。
・配管工事・電気工事:中間検査終了後、建物内に水やガスなどを供給するための設備を設ける配管工事、また、配線、照明設備、コンセント、スイッチ、エアコン、電気温水器を取り付ける電気工事を行います。
・断熱工事:断熱材を建物の外壁・天井・床といった部分に入れたり、複層ガラスや二重サッシ、断熱ドアなどを設置する工事です。
・外装工事:外から見える設備や装飾を施す工事で、外壁工事、雨樋工事、屋上工事といった種類があり、屋根工事も外装工事に含まれます。
・内装工事:建物内部の仕上げを行う工事になります。主な内容としては、壁や天井の塗装、クロス張り、床材の張り替え、建具(扉・窓)の取り付け、タイル、カーペットといった内装仕上げ材の施工などがあります。また、階段や手すりなどの設置も行います。なお、内装工事には、キッチンやバスルームなどの取り付けなども含まれます。
・完了検査:工事が完了したら、4日以内に各地方自治体の特定行政庁、民間の指定確認検査機関などに建築確認を申請。申請を受けた日から7日以内に実施します。この検査で、その建物の構造や設備、敷地などが法令に適合しているかどうかが確認され、適法と認めれば「検査済証」が交付されます。
・引渡し:建物が完成したら、施主への引渡しを行います。この際、施工者は施主に書類や設備機器の保証書、取扱説明書などの重要書類を渡します。
以上が、おおまかな家作りの流れです。ざっと紹介しただけでも、一軒の家が建つまでには数多くの工事が必要です。次に、これらの工事に、大工さんがどのようにかかわっているのかを見ていきましょう。
大工さんの主な種類
「大工さん」と聞くと、「家屋やビルの建築現場で働いている職人さん」というイメージを抱く人は多いと思われます。間違いではありませんが、工事や仕事内容によって、従事している大工さんは異なります。また、建物以外を作る大工さんも存在します。そこで大工さんにはどのような種類があるのか、どのような仕事を行っているのか、それぞれの特徴について解説します。
家屋大工・木造大工・建築大工・建て方大工:設計図に基づき、柱や梁、壁、床てなどの構造材料を加工から、取り付け・組みたて作業までを行い、様ざまな木造構造物を作るのが主な仕事です。また、工事の段取りを整え、工程を管理するのも大工の役割のひとつといえます。一般に「大工さん」といえば、これらを指すことがほとんどで、ほかに「住宅大工」「家大工」、昔ながらの「町大工」と呼ばれることもあります。新築はもちろん、増築・改築、リフォームやリノベーションなど仕事は幅広く、技術や工法が日々進歩しているため、専門知識のアップグレードも必要です。
型枠大工
建築現場で、各建物に合せたコンクリート打ち込み用の型枠を作る「型枠工事」を担当。用意した型枠を組み立て、生コンクリートを入れ、固めた後に型枠を外すというのが主な仕事内容で、一般住宅はもちろん、コンクリート造のビルやマンションにもなくてはならない存在です。なお、型枠工事における垂直精度は±3mm以内が許容範囲。これを外れると建物の強度や完成度に問題が出るため、精密な仕事が求められます。
造作大工
天井や壁、窓枠をはじめ、床、階段、敷居、鴨居など、主要構造部以外の内装を、木材を使用して作り上げていく仕事を担当します。また、玄関枠や木製建具枠などの取り付け、設備機器、下駄箱などの下地や据付株(建物の柱や梁などの荷重を支えるため、地面に埋め込んで固定する木材や鉄材)の取り付けも造作大工の仕事です。なお、壁や床、天井などにクロスや壁紙などを貼っていく工事は、造作工事が終わったあと、内装仕上げ職人が行います。
建具大工
建物の「建具(窓やドア、障子、引き戸、格子戸ほか)」を製作・設置するのが仕事。木材や金属、プラスチックなど、様ざまな素材を用いて、建物の内装や外装に建具を取り付けます。
宮大工
寺社仏閣をはじめ、歴史的建造物の建築や修繕を行う仕事を行います。高度な専門知識と確かな技術力が求められ、国の重要文化財など、重要な建造や補修を任せられることもあります。

上記の他に、住宅の屋根を構成するための「屋根大工」、外壁専門の「外壁大工」などもあり、手がける建物や習得した技術によって、複数の種類に分けられます。また、時代が変わり、稀少になってしまった下記のような職種もあります。
数寄屋大工
主に茶室(数寄屋造り、書院造り)を造る大工さんで、専門知識、細かな細工を行う技術などが必要とされています。
船大工
その名の通り、屋形船や和船、帆かけ船といった船を建造する仕事を行います。かつて木造船が主流であった頃は多くの大工さんがいましたが、現在はかなり減少しているとのことです。
なお、大工さんとして「一人前」といわれるまでには、それなりの時間がかかります。たとえば、設計の自由度が高く、施主が希望するデザインや間取りの「注文住宅」を施工できる大工さんであれば5~10年、ハウスメーカーによる建売住宅の大工さんなら3年程度の修業が必要です。
大工と左官職人はどこが異なる?親方と棟梁の違いは?
建築現場では、大工さんの他に多くの作業員が働いており、その中に「左官」「鳶」と呼ばれる職人さんがいます。大工さんと似たような仕事をしているように見えますが、鳶職の基本は「高所での作業」や「建設現場の足場作りほか、作業員のサポート」、左官職は、「コテを用いたセメントやモルタル、珪藻土などによる、外壁や内壁の仕上げ」「玄関・ポーチといった土間の仕上げ・洗い出し、タイル張りなどの施工」が主な仕事になります。
また鳶職は足場だけでなく、大型機械などの重量物をクレーンで搬入、設置・解体する「重量鳶」、高所に鉄骨をクレーンで釣り上げ、鉄骨を組み立てる「鉄骨鳶」も活躍しています。
現場に行くと「棟梁」「親方」と呼ばれる大工さんがいます。どちらも大体がベテランで、現場を仕切る、施主と交渉することも少なくありません。棟梁とは、建築現場で工事を指揮・監督する大工の責任者のことです。また、弟子や見習の技術指導なども行います。なお、棟と梁が家を支える重要な部分であることから、国や一族の頭や統率者を指す言葉としても使われます。一方の「親方」も同様の仕事をしますが、大工さん限定の呼び方ではなく、左官職人や鳶職人にも後進を指導する親方はいます。つまり棟梁は、大工さん(石工も含む)の尊称で、それ以外の親方を棟梁と呼ぶことは少ないそうです。
大工さんに役立つ資格や免許
基本的に学歴や資格は問われませんが、大工さんに役立つものはあります。取得しておくと給与や待遇面で有利な資格は下記の通りです。
建築大工技能士(1~3級)
都道府県職業能力開発協会によって実施される国家資格です。木造建築物の大工工事に必要な技能を認定するもので、1~3級が設けられており、この資格を取得すれば、一定以上の技術を持っていることを証明できます。なお、受験する級によって必要な実務経験は異なります。

取得に必要な実務経験
・1級建築技能士:実務経験7年以上
・2級建築技能士:実務経験2年以上
・3級建築技能士:実務経験6ヶ月以上
木造建築士
国土交通省が管轄する国家資格です。2階建て、かつ延べ面積が100㎡以上300㎡以内の木造建築物の設計や、工事管理などに従事することができます。二級建築士も、ほぼ同様の仕事が可能ですが、木造建築士の場合、古民家や寺社仏閣といった、専門的知識が必要な伝統的な建築物の工事や管理にも携われます。
取得に必要な実務経験
・大学:建築課程卒/不要、土木課程卒/2年以上
・短期大学:建築課程卒/不要、土木課程卒/2年以上
・高等専門学校:建築課程卒/不要、土木課程卒/2年以上
・高等学校(建築・土木課程卒):3年以上
・建築設備士:実務経験不要
・建築に関する学歴なし:7年以上
二級建築士
二級建築士は国家資格で、取得すると建物の設計や工事監理、契約に関わる事務、工事現場の指導監督などを担当することができます。扱える建物は、木造建築物なら3階建てまでが基本。高さ13m、軒高9mを超える建物、延べ面積1000㎡以上の建築物設計は認められていません。RC造、鉄骨造など、木造建築物以外の場合は、さらに制限が厳しくなります。
主に戸建て住宅ほどの小規模なものに制限されます。そのため、戸建住宅の設計を対象とした資格といえます。
取得に必要な実務経験
・所定の指定科目を履修して大学、専門学校・工業高校を卒業した場合、実務経験は不要
・上記以外:実務経験7年以上
木造建築物の組立て等作業主任者
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、またはこれに伴う屋根下地や外壁下地の取付け作業において、安全面などの監督・指導にあたる責任者で、国家資格とされています。各都道府県の講習会を受講することで取得可能です。
受講に必要な実務経験
・木造建築物の構造部材の組立て、またはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取付け作業に3年以上従事した経験をもつ者
・大学や高専または高校で、土木・建築学科を専攻し卒業した後、2年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を持つ者
・職業能力開発促進法に基づく一定の訓練修了後、2年以上の実務経験のある者。
建築施工管理技士
1・2の級があり、国土交通大臣指定機関が実施する国家試験です。1級建築施工管理技士の仕事は、鉄筋・大工工事・内装の仕上げ工事ほか、すべての施工計画を作成、現場での工程管理、品質・安全面の指導を行う重要な技術資格です。工事の規模に上限がないため、大きな規模の建築現場を担当することができます。
取得に必要な実務経験
・大学、専門学校を卒業し「高度専門士」と称する者:指定学科/3年以上、指定学科以外/4年6ヶ月以上
・短期大学・ 高等専門学校、専門学校を卒業し「専門士」と称する者専門学校を卒業し「高度専門士」と称する者:指定学科/5年以上、指定学科以外/7年6ヶ月以上
・高等学校・専門学校:指定学科/⑽年以上、指定学科以外/11年6ヶ月以上
・その他:15年以上
これらの資格を取っておくことで活躍の場が広がり、受注数の増加につながる可能性が期待できます。また、転職の際、有利に働くこともあるといえるでしょう。
大工さんに自動車運転免許は必要?
自動車運転免許、各種運転免許は、大工さんの仕事に必ずしも必要ではありません。ただ、一般的な就職に「要普通免許(AT、MT、第一種、第二種)」が少なくないように、建設会社や工務店の中にも、免許を必須とするところはあります。その理由は、電車といった交通機関での移動が難しい現場に向かう、工事に必要な資材を運ぶ場合、自動車での移動が欠かせないからです。不便な場所には、会社のバスやワゴンでまとまって行くことも多いですが、たとえば就職活動の際、運転免許を持っている方が有利になることもあるようです。
また、大型免許(第一種、第二種)や小型特殊免許・大型特殊免許(第一種、第二種)、クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士といった車両の免除を取得していると仕事の幅も広がり、手当てが付くこともあるので、取得しておくのもいいでしょう。
大工さんのやりがい
学歴や資格は問われないとはいえ、一人前の大工さんになるには、技術や知識が要求されます。それを得るためには、現場で経験を積まなくてはなりません。また修行の傍ら、資格の勉強が必要なこともあるでしょう。

しかし、建物の大小にかかわらず、「形として残るもの」を作ることができます。一棟の家が完成し、施主さんの喜ぶ顔を見た時、苦労を忘れるという大工さんもいます。道のりは平坦ではありませんが、大工さんはやりがいのある仕事だといえるでしょう。