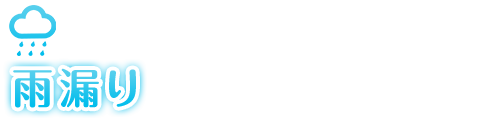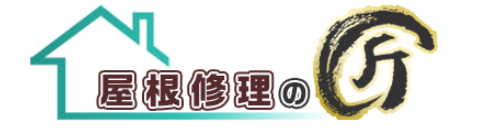人手不足を支える「新しい戦力」

日本の建築・建設業界では、長年にわたって深刻な人手不足が課題とされてきました。高齢化の進行や若者の業界離れが続く中、現場を支える「新しい担い手」として注目されているのが外国人労働者の存在です。特に2010年代後半以降、建設現場における外国人の比率は年々上昇し、今や全国の建設現場においてその姿を見ない日はないといっても過言ではありません。
厚生労働省が発表した「外国人雇用状況の届出状況」によると、2023年10月末時点で建設業に従事する外国人労働者の数はおよそ14万5千人。これは2016年時点の約4万人から7年で約3.5倍に増加したことを意味します。また、外国人労働者全体のうち建設業に従事している割合も、2016年には約3.8%だったのに対し、2023年には7%を超えており、急速な増加傾向が見て取れます。
とくにここ数年は、東京オリンピックの建設特需や、震災からの復旧工事、老朽化したインフラの改修需要などが続いており、それに対応するための労働力として、外国人の存在感がますます大きくなっています。これらの背景には、単なる労働力確保だけでなく、多様化する現場への適応力や新しい技能の導入という視点も含まれているのです。
技能実習と特定技能という制度

日本の建設現場で働く外国人の多くは、「技能実習」や「特定技能」といった在留資格で滞在しています。特に技能実習制度は、1993年の創設以来、外国人が日本で技術を学び母国へ持ち帰ることを目的に運用されてきました。しかし実態としては、労働力として建設業界を支える存在となっているのが現状です。
2023年には、建設業で働く技能実習生が約8万8千人、特定技能の在留資格を持つ外国人が約2万4千人を数えました。とくに特定技能は、2019年に新設された制度で、試験や日本語能力の要件をクリアすれば、より長期間の在留が可能になり、家族帯同も将来的には認められる見通しとなっており、建設業界からの期待も高まっています。
この2つの制度の役割分担としては、技能実習が「教育的側面」を重視する一方、特定技能は「即戦力としての労働力確保」を目的としている点が大きな違いです。そのため、今後は技能実習から特定技能への円滑な移行が、建設業にとって重要なテーマとなるでしょう。
また、制度上のステップアップが明確になれば、外国人労働者自身の意欲向上にもつながります。「日本で長く働きたい」「もっと専門的な技能を身につけたい」という希望を実現するための環境が整備されることで、優秀な人材の定着が進み、日本人職人との協業もよりスムーズになると期待されています。
国別の内訳と地域偏在
建設業に従事する外国人の出身国を見ると、ベトナム、中国、フィリピンが上位を占めています。特にベトナムからの労働者は近年大きく増加しており、2023年末時点で全外国人建設労働者の4割以上を占めるとも言われています。これには、両国間の技能実習制度における協定や、日本での生活・就労に対する高い志向が背景にあると考えられます。
また、外国人労働者の就業は都市部だけでなく、地方にも広がっています。むしろ地方の方が労働力不足が深刻であり、ある自治体では建設現場の3割以上が外国人によって支えられているという例もあります。このような地域偏在は、外国人労働者の定着率や生活支援のあり方を再考する必要があることを示しています。
地方では、日本語学校や通訳の数が限られており、行政や自治体、地域社会による受け入れ体制の差も浮き彫りになっています。一方で、地域住民と交流イベントを開催したり、自治体が住宅支援や相談窓口を設けたりするなど、先進的な取り組みを行う地域も増えてきました。こうした地域の取り組みは、今後の外国人受け入れのモデルケースとして注目されています。
増加に伴う課題と現場の声

外国人労働者の受け入れが進む一方で、その環境整備が追いついていないという課題も浮き彫りになっています。たとえば、日本語での安全教育や作業指示がうまく伝わらないことから、労災リスクが高まるケースも報告されています。また、文化や宗教の違いによる職場でのコミュニケーションの難しさ、住宅・生活環境の不備、制度的な支援の不足など、多くの課題が現場には存在しています。
さらに、受け入れる企業側の体制にも差があり、「外国人を雇いたいが、手続きや教育の負担が大きすぎる」といった声も根強くあります。実際、建設業における外国人雇用経験のある事業所は全体の3割弱にとどまっており、まだ多くの企業が慎重な姿勢を崩していません。
制度改革の必要性と今後の展望

こうした状況を踏まえ、政府は現在、技能実習制度の抜本的な見直しを進めています。これまで建前と実態が乖離していた技能実習制度に代わり、実際の労働力としての位置づけを明確にした新たな制度の創設が議論されています。加えて、特定技能制度の対象拡大や、特定技能2号の条件緩和など、より長期的かつ安定的な在留を可能とする方向に制度は進化しようとしています。
また、送り出し国との連携強化や、悪質な仲介業者の排除、就労後の生活支援体制の構築も重要な課題です。こうした取り組みが進むことで、外国人労働者が安心して長く働ける環境が整えば、建設業界における人材不足の解消にとって大きな一歩となるでしょう。
多文化共生の現場づくりへ

今後、建設業における外国人労働者は、単なる「人手不足を補う存在」ではなく、「新しい価値を創造する人材」としての側面が強まっていくはずです。多様な文化的背景を持つ人材が協力し合い、より効率的で安全な現場を作り上げていくことが求められます。
そのためには、言語・文化・宗教の違いを尊重しながら、互いに理解し合える職場環境の整備が必要です。企業や現場責任者のリーダーシップ、そして政府の後押しが不可欠となるでしょう。加えて、日本人労働者側にも異文化への理解や対応力が求められる時代になっていることを忘れてはなりません。
おわりに

建設業界における外国人労働者の推移は、単なる統計上の数字ではなく、日本社会が直面する「労働力不足」と「多文化共生」という二つの課題を象徴しています。今後、外国人材が建設業界でより安定的に活躍できるよう、制度・教育・職場環境の整備を着実に進めることが、業界全体の持続可能性に直結していくのです。
これからの建設業界は、外国人とともに新しいステージへと歩み出そうとしています。