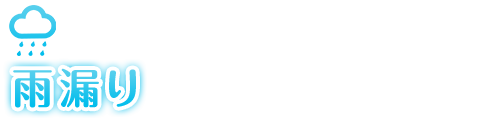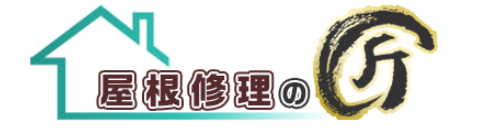建築業界は今、日本のあらゆる産業の中でも特に深刻な人手不足に直面している分野のひとつです。
少子高齢化に伴う労働人口の減少、若年層の建設業離れ、過酷な労働環境のイメージなど、複数の要因が重なり、すでに現場では人材確保が困難になっています。そして、これから20年後、さらにその傾向は加速していくことが予測されています。
では、その未来において、特に人手不足が深刻になる可能性が高い建築業界の業種とは何なのでしょうか?このコラムでは、人口動態や社会の変化、業界の構造をふまえて、将来的に人手不足が顕著になる職種を具体的に挙げながら考察していきます。
なぜ建築業界は人手不足が進むのか?

建築業界が人手不足に陥っている要因は大きく分けて3つあります。
1. 労働人口の減少
日本全体の出生率が低下しており、今後も労働人口の減少は避けられません。特に若年層が少なくなるため、肉体労働を伴う建設業に入ってくる人の割合はますます減っていくことが予想されます。
2. 高齢化と引退の波
現在、建築現場で働いている職人の多くが50代〜60代以上。今後20年の間に多くが定年・引退を迎えるため、そのスキルや技術が継承されないまま業界から人材が一斉に抜けていく「団塊引退ショック」が現実味を帯びています。
3. 若手の建設離れ
「きつい・汚い・危険(いわゆる3K)」という旧来のイメージが根強く、ITやサービス業などへの流出が止まりません。新卒で建設業を選ぶ人は年々減っており、将来もその傾向は続くと見られます。
20年後に特に人手不足になると予測される建築業界の業種

それでは、具体的にどのような職種が深刻な人手不足に陥る可能性が高いのでしょうか。以下に、今後さらに需要が高まる一方で、担い手が減少していく業種を挙げていきます。
1. 左官職人
左官とは、モルタルや漆喰などの材料を用いて壁や床の仕上げを行う職人のこと。日本の伝統的な建築技術であり、特に歴史的建造物や和風建築では欠かせない存在です。
しかしながら、左官職人は非常に高齢化が進んでおり、若手の数が極端に少ない業種の一つです。しかも、技術の継承には時間がかかるうえ、簡単に機械化できるものでもありません。
そのため、20年後には「やり手がいない」状態になる可能性が非常に高く、需要があっても施工できないという事態が起きるかもしれません。
2. 電気工事士
電気設備の工事は新築・改修を問わず必ず必要です。また、スマートハウスやEV充電設備など、住宅における電気配線の需要はむしろ増えていく一方です。
にもかかわらず、電気工事士の高齢化も進んでおり、国家資格が必要なことから新規参入のハードルも高い職種のひとつです。将来的には住宅やビルの「電気インフラを整備できる人がいない」という問題に直面する可能性があります。
3. 給排水・配管工
水回りの工事に携わる給排水設備工や配管工も、極めて人手不足が深刻化すると見られています。リフォーム需要の増加や老朽インフラの更新が加速する中、現場の数は増える一方で、それをこなせる職人が激減しているのが現状です。
こちらも国家資格が必要な分野であり、育成には時間がかかるため、20年後には「ライフラインを担う人材不足」が顕在化すると予想されます。
4. 型枠大工・鉄筋工
建物の骨組みをつくる型枠大工や鉄筋工は、建築の基礎を支える非常に重要な職種です。しかし、こちらも同様に高齢化と新規参入の少なさから、現場が回らなくなる可能性が指摘されています。
特に鉄筋工事は重労働である上に、専門性が高く、安易にロボット化もできないため、人手不足の深刻度が高まるでしょう。
ロボットやAIは代替になるのか?

最近では建設業界でもロボットやAIの導入が進みつつあります。たとえば、建設用ドローンによる測量や自動溶接ロボットなどが導入され始めています。
しかし、職人技が必要とされる左官や、細かい判断力が求められる電気・配管工事の現場では、完全な自動化はまだまだ難しいのが現状です。むしろ、ロボットと人間が協力し合う「協働」が主流になるため、やはり「人」の手と頭が必要なのです。
今後の建築業界に必要な対策とは?
20年後の深刻な人手不足に備えるには、今から以下のような対策が必要です。
- 若者への積極的な広報と魅力発信:建設業のやりがいや収入の安定性などを正しく伝える
- 教育制度の充実:OJTだけでなく、学校や民間研修での技術教育を強化する
- 外国人材の活用と受け入れ体制の整備:技能実習生制度を超えて、永続的に働ける環境を整備
- 働きやすい職場環境づくり:休暇制度や労働時間の改善、安全対策の徹底など、労働環境の見直しも必要です
さらに、デジタル技術を活用した業務効率化も急務となっています。図面の電子化や施工管理アプリの導入、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に進めることで、現場の負担を軽減し、若者にとっても親しみやすい職場環境をつくることができます。
また、女性やシニア世代の活躍を促すため、力仕事以外のポジションや時短勤務の制度化も検討すべきです。多様な人材が安心して働ける現場こそが、将来の建築業界の基盤となるのです。企業ごとの取り組みだけでなく、業界団体や行政も連携し、包括的な支援策を打ち出すことが今後の持続的成長には不可欠でしょう。
まとめ

今後20年で、建築業界の人手不足はさらに深刻化すると予想されます。特に、左官職人、電気工事士、配管工、型枠大工や鉄筋工などは、高齢化と若手不足、技術の継承難という三重苦に直面し、事業の継続さえ困難になる場面も出てくるでしょう。
だからこそ、今から次世代の担い手を育てる仕組みづくりが急務です。建築は人々の暮らしを支える基盤であり、社会インフラそのものです。その担い手がいなくなるという事態は、単なる業界の問題ではなく、国全体の課題でもあるのです。
これらの職種は、社会インフラや生活基盤に直結する仕事であり、将来的に人材が足りなくなると、建設プロジェクトの遅延やコスト上昇、さらには生活インフラの維持にも影響が及ぶ可能性があります。特に地方の中小工務店や公共事業を担う建設会社では、若手を確保できないことで事業縮小や廃業を余儀なくされるケースも出てくると考えられます。
こうしたリスクを回避するためには、今から技能教育を充実させるだけでなく、建設業の魅力をもっと積極的に発信していく必要があります。IT技術と組み合わせたスマート建築、女性やシニア層の参入促進、柔軟な働き方の導入など、多様なアプローチが求められるでしょう。
建設業界は人の暮らしを支える基幹産業であり、これを未来に繋げるためには、業界全体が変革を続けることが不可欠です。