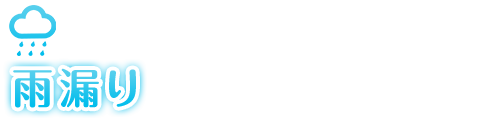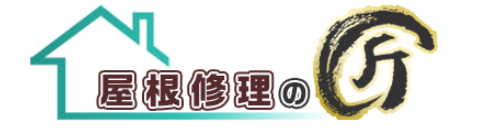若い人材を採用しても定着せず、離職率の高さに悩む建設業の事業者や責任者は少なくありません。高齢化が進行する建設業界では、次世代の担い手を採用し、技術を継承することが急務です。
そのためには、人材の定着を目指し、離職率を低減することが必要です。離職率を下げるためには、まずその原因を明確に把握することが重要です。
この記事では、建設業の離職率の現状と、その離職率が高い理由について詳しく解説します。
また、採用した人材が定着するためのヒントやアイデアもご紹介します。
建設業界の離職率はどのくらいか?

「離職率」とは、その職業に就いた人がどの程度の割合で辞めているかを示す指標です。
建設業界の離職率は高いとされていますが、厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況(平成28年3月卒業者の状況)」によれば、大学卒業者の27.8%、高校卒業者の45.3%が就職後3年以内に離職しています。
高卒離職率が特に高い傾向

大学卒の平均離職率は32.0%であるのに対し、建設業では27.8%と平均より低い離職率となっています。一方で、高校卒の平均離職率は39.2%であるのに対し、建設業では45.3%と平均よりもかなり高い離職率となっています。
建設業の離職率が高いと言われていますが、実際のところ大学卒の場合はそれほど高くありません。しかし、高校卒の場合は他の産業と比較してかなり高い離職率を示しています。
雇用が不安定

建設業は日給制が一般的で、社員として採用することが少ない業界でした。しかし、国土交通省の資料によると、現在の建設業就業者数500万人のうち、契約社員などの非正規雇用は19%を占めています。これは、製造業の27%と比較しても多くはありません。
それにもかかわらず、建設業界には依然として日給制の文化が根強く残っており、現場で直接作業を行う技能労働者のうち、6割以上が日給制です。日給制では、天候により作業が中止されると収入が減少し、収入が一定しないため、長期的に働くことに不安を感じる若年層が多いです。
離職率が高くなる理由

- 休みが少ない
建設業界では、週休2日制が普及していないため、休みが少ないことが離職の一因とされています。多くの企業が週休2日制を採用している現代では、プライベートの時間を大切にする人々が増えているため、この点が大きな問題となっています。 - 家族や友人と休みが合わない
建設業界では土日休みが少ないため、家族や友人と休みが合わず、一緒に過ごす時間が取れないことが離職の理由になります。現代では、家族や友人との時間を重視する人が多いため、この問題は大きいです。 - 長時間労働
建設業界では、残業や休日出勤が慣習化しており、長時間労働が常態化しています。他の業界と比べて労働時間が約1.2倍長く、納期を守るために過度の労働が求められることが多いです。 - 人間関係の難しさ
建設業界では多様な職種の人々が働いており、人間関係が複雑になりがちです。特に高齢化が進んでいるため、価値観や考え方の違いから、良好な人間関係を築くことが難しいことが離職の原因となっています。 - 体力的な負担
建設現場は天候に関係なく作業が行われるため、体力的に厳しい仕事が多いです。特に屋外での作業が多く、体力的な負担が大きいため、この点が離職率の高さに繋がっています。 - 厳しい納期
建設業界では納期が厳しく、天候にかかわらず作業を続けなければならないことが多いです。これにより、労働環境が悪化しがちで、結果的に離職率が高くなっています。 - 発注元からの厳しい要求
建設業界では、発注元からの無理な要求やトラブルが頻発します。設計変更や過度の要求が発生し、これがストレスとなって離職に繋がることがあります。 - 給料が見合っていない
長時間労働や休日が少ないにもかかわらず、給料がそれに見合っていないことが不満となり、離職率を高めています。仕事がきついのに給料が低いという状況が続いています。 - 評価制度への不満
建設業界では実績に基づく評価制度がありますが、少しのミスも許されない厳しい評価基準が離職の一因となっています。実績を積むことが難しいため、不満が溜まりやすいです。 - 新卒者への負担が大きい
建設業の現場では少人数で作業することが多く、新卒者であっても大きな責任が課されます。これにより、新卒者にとって過重な負担となり、離職率が高くなっています。
これらの理由から、建設業界の離職率が高いと言われているのです。
離職率を下げるポイント

建設業は人手不足に直面しており、その原因の一つに離職率の高さが挙げられます。人手不足を解消するためにも、離職率を低下させるための取り組みが必要です。ここでは、離職率を下げるための7つのポイントを紹介します。
- 福利厚生を整える
建設業界の離職率を下げるためには、社会保険への加入や福利厚生の充実が必要です。建設業の雇用者のうち、非正規雇用者が約2割を占めており、彼らの福利厚生を充実させることで、離職率の低下が期待されます。 - 社員の年齢層を幅広くする
建設業界の人手不足と高齢化を解消するためには、女性社員や外国人労働者の積極的な採用が重要です。多様な人材を活用することで、社員の年齢層を広げ、高齢化を防ぐことができます。 - 勤務時間を正しく管理する
長時間労働が問題となっている建設業界では、週休2日の徹底や適切な仕事量の管理が求められます。国土交通省や日本建設業連合会は、週休2日モデル工事の拡大や生産性向上を目指した取り組みを進めています。 - 完全週休2日制を導入する
休みが少ないことが離職の一因であるため、完全週休2日制を導入することが重要です。日本建設業連合会は、建設現場を土日に完全閉所する目標を立て、休日を徹底させる取り組みを進めています。 - 若い社員の話が聴ける環境を整える
若い社員と年配社員の年齢差が大きいため、若い社員の意見を積極的に聞く環境を整えることが重要です。日常的にコミュニケーションを取り、若い社員が話しやすい雰囲気を作ることが求められます。 - 採用時に長く働ける人を採用する
新卒採用時には、建設業を希望する人材や自社にマッチする人材を見極め、長く働ける人を採用することが大切です。会社の仕事内容や働き方を正しく伝え、相手の理解を得ることでミスマッチを防ぎます。 - ICTなどを利用した業務の効率化
長時間労働が常態化している建設業界では、ICT技術を活用して業務を効率化することが重要です。遠隔作業指示や情報共有が容易になることで、若い社員が働きやすくなり、離職率の低下に繋がります。
これらの取り組みを実施することで、建設業界の離職率を低下させ、人手不足の解消に寄与することが期待されます。
原因を理解すれば離職率は改善できる

建設業は長い間、長時間労働や週休2日制が徹底されていないことから、いわゆる「3K」(きつい・汚い・危険)のイメージが強く、これが離職率の高さに繋がっている大きな要因です。
離職率が高いことには相応の理由があり、これらの原因を理解し、対策を講じることで、離職率を改善し、人手不足の解消につなげることができるでしょう。以下のポイントを実行することで、建設業界の労働環境を改善し、働きやすい職場を作ることが期待されます。